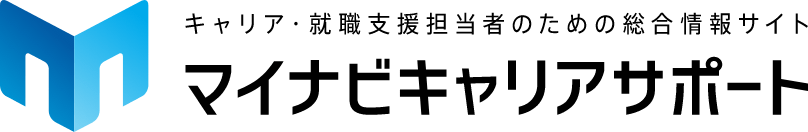1950年に開学した沖縄唯一の国立大学である琉球大学では、現在7学部・8研究科を有し、地域と連携しながら多様な教育・研究活動を展開。さらに、地域と世界に貢献する人材育成を理念に掲げ、次世代の担い手を育成しています。そんな琉球大学では、主に低学年次の学生を対象とした必修科目である「キャリア形成入門」を筆頭に、体系的かつ実践的なキャリア教育に注力しているとのこと。今回は、学生の思考習慣に焦点を当てたキャリア教育の考え方と現場での具体的な取り組みについて、企業での勤務経験を持ち、企業研修の実績も豊富なグローバル教育支援機構 キャリア教育支援部門 准教授の武田氏にお話を伺いました。
Profile

武田 和久 氏
琉球大学 グローバル教育支援機構 キャリア教育支援部門 准教授
大学卒業後、メーカーや保険会社の営業職を経て自身でコンサルティング会社を設立。独立後は管理職・リーダー職を対象にしたマネジメントやリーダーシップ、モチベーションなどに関する研修・講演活動を行う。2019年から都内の大学で教員として学生の成長に携わり、2023年より現職。
低学年次からの必修授業でキャリアを自分ごとにする

―まずは、現在、主に低学年次を対象に必修科目になっている「キャリア形成入門」について教えてください。
「キャリア形成入門」は、今年度から主に低学年次の必修科目として実施しています。1クラス最大150名×11クラスで、年間1,000名以上の学生が受講していることになります。
キャリアというのは、学年が上がってから考えれば良いというものではないと個人的にも強く感じています。特に沖縄という地域は地域特有の課題も多く、そうした地域課題に向き合える人材を育てるためにも、早い段階から社会との接点を設ける必要があります。
また、これも地域柄なのだと思いますが、大らかな学生が多いと個人的に感じるため、キャリアを自分ごととして捉えて行動に移せるように、学生のモチベーションを高める必要があると感じています。
ARCSモデルに基づく計算されたキャリア支援

―低学年の学生のモチベーションを高めるためのコツについてもお伺いできますか。
実は、私は大学での教育に携わる前から、企業の管理職やリーダー職を対象にしたマネジメントやモチベーションなどに関する研修を行ってきました。その時から「ARCSモデル(アークスモデル)」という動機付け理論をよく使っており、その理論をキャリア教育でも活用しています。
ちなみに、ARCSとはAttentionの注意、Relevanceの関連性、Confidenceの自信、Satisfactionの満足という4つの要素からなる教育理論です。
―具体的にどのようなことを行っているか教えていただけますか?
最初の「注意」の段階では、授業の冒頭に学生が興味を持ちそうなニュースや事例をパワポで簡単に紹介し、その後、3分ほどのグループディスカッションを入れるようにしています。学生たちに「自分にも関係があるかも」と感じてもらうことがスタートラインなんです。
「関連性」では、学生に近い他の学生のエピソードや、私が以前指導したゼミ生の話などを盛り込むようにしています。歳の離れた大人の話よりも、自分と近い世代のリアルな話の方がより響くからです。
そして、「自信」については、毎回の課題を丁寧にフィードバックしています。さらに、高評価のものをいくつか取り上げて授業内で紹介すると、取り上げられた学生は「自分のことだ」と自信につながり、これらの経験が学生たちの「満足」につながっていきます。
目的の先にある目標が生き方を豊かにするベースになる

―実際、学生にはどのような課題を出しているのでしょうか。
まずは、毎週提出してもらっているキャリア行動レポートですね。200字ほどで、キャリアのためにどんな行動をしたかを書いてもらいます。その小さな行動の積み重ねが大切です。習慣にすることに意味があると考えています。
なぜなら、キャリアというものは、期限のないことの連続だからです。学生は、目の前の単位取得という目標に一生懸命になりがちで、どうしても期限や締切があるものを優先してしまいます。
しかし、キャリアは、むしろ期限のないことをどう積み重ねていくかなのです。何のために学ぶのか、どうなりたいから就職するのか。目標ではなく、目的を自分の中で明確にしてほしい。
だからこそ、1年生のうちから目的を考える習慣を作る必要があると思っています。そして、その習慣こそが学生の自信になり、やがて主体的な行動へとつながります。正解がある問いでなくても良いのです。目的を考えることが、生き方を豊かにするベースになっていくと感じています。
―キャリア形成入門を続けてきて、見えてきた効果はありますか?
授業を履修した学生からの個人面談の申込が、2年前と比べて約1.5倍に増加し、進路について主体的に考える学生が増えているように感じています。また、インターンシップ合同説明会や業界研究講座の参加者数も年々伸びていますね。
さらに、このキャリア形成入門は学生に対して行う授業評価アンケートにおいて高い評価を受け、琉球大学における全11区分・850超の共通教育科目の中から2024年度のプロフェッサー・オブ・ザ・イヤーに選出されました。
1年生で必修のこの授業で、マインドセットされれば、他の授業に対する姿勢も変わっていくと思います。
自分自身のキャリアに向き合うための行動を促す

―1年生以外の学生に向けたキャリア支援はどのような取り組みをされていますか?
一つは、「実践キャリア形成」という授業ですね。2024年度に新しく開講したもので、主に2年生以上の学生を対象としています。「キャリア形成入門」がマインドをつくる授業だとしたら、「実践キャリア形成」はアクションを起こす授業です。
授業の8割はワークで構成されており、より深い自己分析をメインに、社会に出るために必要なスキルに関しても自分を深く見つめてもらう構成にしています。単位を取りながら、自然とキャリアの準備ができるように工夫されているのもこの授業のポイントです。
他にも、「課題解決プログラム」という授業もあります。那覇市役所や地元企業と連携しながら、学生がリアルな地域課題に挑戦する実践型学習の機会も増やしています。
―では、キャリア支援を行っているうえで、課題に感じていることはありますか。
「キャリア形成入門」は主に1年生を対象にした授業なので、何を相談して良いかまだわからないという学生の声は課題だと感じています。しかしながら、わからなくても、まずは話すことがスタートだと伝えていて、学生に寄り添うことを意識しています。
アドバイスをするというよりも、とにかく学生の中でモヤモヤしているものを言葉にして出してもらう。そうすることで、新しい情報が自然に入ってくるような環境づくりを心がけています。
それに加えて、授業内では、ライフラインチャートを描くワークもやっています。人生の山や谷を整理しながら、自分自身を知ってもらうための時間です。
他の学生と共有することで「自分だけではない」と安心する声も多く、より一層自身のキャリアに向き合えるようになっていると感じています。
多様化する今だからこそ質の高い刺激を与えるために

―最後に、他大学の皆さまへメッセージをお願いします。
キャリア教育は、学生自ら学びに来るものではないので、大変に感じている方もおられると思います。日々、学生の将来に向き合いながらキャリア支援に取り組んでいる全国のご担当者の皆さまに、心より敬意を表します。
学生の価値観や進路の選択肢が多様化する今、キャリア支援の在り方も大きく問われていると感じています。だからこそ、学生には、質の高い刺激をできるだけ与えたい。そのためにも、大学の枠を超えた情報共有や交流の場がもっと増えてほしいと考えています。
互いに学び合い、励まし合えるようなネットワークが、キャリア教育全体の質を底上げする鍵になると思います。私自身、まだ試行錯誤の中にありますが、他大学の皆さまの取り組みや知見に学びながら、学生一人ひとりの成長に丁寧に寄り添っていきたいと思っています。
Editor’s Comment

琉球大学 グローバル教育支援機構 キャリア教育支援部門の武田先生に取材させていただきました。1年生の必修科目「キャリア形成入門」導入や2年生向けキャリア科目の新設、全国規模の企業が集まる「琉球キャリアフェス」の開催など多くの支援を常に学生目線に立ちながら取り組まれている姿が印象的でした。ご自身の講師経験も交え、モチベーションアップに関する理論を取り入れながら学生に「目的を考える思考習慣」を身につけることの大切さを軸に置く指導は、インターネットやAIによって即座に回答が得られる時代にこそ、人間自身が持つべき能力である、というメッセージを感じました。同時に「将来や仕事をすることに対してワクワク感も持たせたい」との言葉に、理論や実践だけでなく、感情も必要なポイントだと気づかされました。
(マイナビ編集長:高橋)
「マイナビキャリアサポート」は
キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです
長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。
より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。