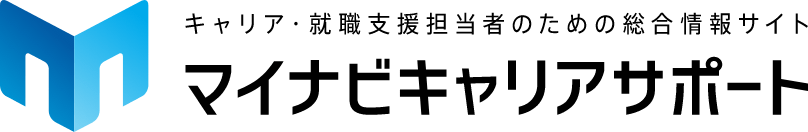令和元年にGIGAスクール構想が打ち出され、1人1台の端末と高速大容量の通信ネットワークの整備をすべく予算が割り当てられました。その結果、教育ICT(情報通信技術)環境の整備は一気に加速しました。令和3年以降は小・中・高校などにおいて1人1台端末の本格的な利活用がスタートし、教育の場でのデジタル学習が身近になる時代が到来しています。
この記事では、大学教育での活用事例を通してデジタル学習のメリットを整理し、キャリア形成支援のポイントについて解説します。
デジタル学習が注目されている背景は?
新型コロナウイルス感染症対策として発令された緊急事態宣言や小・中・高校における一斉臨時休校などの措置は、教育のデジタル化を加速させるきっかけとなりました。学生は外出自粛期間にオンラインでの学習方法に触れることが多くなり、教室でおこなっていた対面型の授業以外の学び方が広がりました。
そして今、デジタル学習に慣れ親しんだ学生が大学に進学する時代となったことで、大学独自のデジタル学習プランを導入検討するケースも見られます。
今後必要とされるデータ活用のための分析スキルやAI関連技術などは、デジタル学習との相性もよく、仕事の合間におこなうリスキリング需要とも相まって、デジタル学習は注目を集めています。
学生がデジタル学習を活用するメリット
学生や教職員が教育の場で利用するデジタル学習のツールは、パソコンやタブレットはもちろん、電子黒板やデジタル教科書、学習を支援するソフトウェアなど、さまざまなものがあります。では、デジタル学習には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
自分のペースで学べる
学校の授業や大学の講義は時間割が定められており、集団で学ぶため、自分の都合で中断することはできません。しかしデジタル学習であれば、個々の理解度や興味関心の度合いにあわせて自分のペースで学ぶことが可能です。
例えば、理解できていない箇所があれば何度も繰り返し見直しながら、理解できるまで学べます。逆に、理解度が高ければスピードを上げて学習することもできます。
場所を選ばずに学習できる
デジタル学習は、パソコンやタブレットなどの端末があれば場所を選ばずに学ぶことができます。そのため、通学などの移動時間や空きコマなどの隙間時間で学習でき、遠方にいても学習できることは学生にとって大きなメリットです。
こうした利便性の高さから、デジタル学習は学生にも広く受け入れられています。
特に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンライン授業の導入が進み、自宅などから効率的に学べる環境が整備されたことで、そのメリットが認識されるようになりました。
こうした背景から、コロナ収束後もオンライン授業の継続を望む学生の声も多く、オンラインと対面のハイブリッド型の授業を導入している大学もあります。
学習のオンライン化が進むなかで、デジタル学習の活用も今後さらに拡大していくと予想されます。
学習の幅を広げられる
対面で授業をおこなう場合は教室の数や収容可能人数などの都合で、受講者を制限せざるを得ませんが、デジタル学習を活用すればより多くの学生が受講できるようになります。学生は自主的に学ぶ内容を選択できるようになり、学習の幅を広げられます。
さらに、近年は学校の授業以外にも手軽に学べる学習コンテンツが数多く公開されており、自分の専攻以外の分野も学べる機会が増えています。
例えば、マイナビが運営する学生向けキャリア学習サービス「My CareerStudy」では、社会人基礎力や、社会に関する情報、将来に向けた情報など、幅広い内容の教育コンテンツを提供しています。
デジタル学習での学びを証明できる
一般的に知識やスキルを証明するためには各種検定試験を経て資格を取得する方法がありますが、普段の学習内容を資格で証明することは難しいでしょう。
しかし、デジタル学習であれば学習履歴や成果をデータとして記録できるため、学びを客観的に証明しやすくなります。学習成果やスキルの習得をデジタルで証明する方法の一つに「オープンバッジ」というデジタル証明書があります。
オープンバッジは、国際標準のツールとして欧米の大学や企業で活用されており、日本でも資格認定団体や企業、大学などでの活用が広がっています。また、ブロックチェーンの技術によりデータの改ざんや偽造が困難な仕組みであるため信頼性が高いとされています。
さらにオープンバッジでは、「スキル」「知識」「参加」といった受講レベルに合わせてバッジが提供されます。大学生にとっては、身に付けた知識やスキルを提示できるため、就職活動などでの効果的なアピールにつなげることもできます。
先述したマイナビが運営する学生向けキャリア学習サービス「My CareerStudy」では、2025年春よりオープンバッジの発行機能を実装し、学生をサポートする体制を強化しています。
大学がデジタル学習を活用するメリット
大学はGIGAスクール構想によりデジタル学習に慣れ親しんだ学生のニーズに対応することが望ましいでしょう。デジタル学習の活用によりどのようなメリットが期待できるのでしょうか。
各学生に合った学習支援がしやすい
デジタル学習の効果を最大限に活かすために、LMS(学習管理システム)の導入を積極的におこなう教育機関は増えています。LMSとは、デジタル教材やツールを活かした学びをマネジメントする際のプラットフォームになるシステムです。カリキュラムの登録や教材コンテンツの配信、デジタル教材の閲覧・活用、学習履歴(成績や進捗状況など)の管理、成果物の提出などが主な機能です。
LMSを活用して学生の学習履歴や成績などの情報を蓄積し、定期的に分析すれば、学習成果の向上につながるようなアドバイスをおこなったり、それぞれの学生ニーズや将来の目標に即した教育プログラムを提案することができるようになります。
デジタル教材で講義を補完できる
デジタル教材を使用すると、時間の都合で解説できない内容や、紙の教材では省略せざるを得ない精密な図や写真、動画などを補完教材として利用できます。
特に、動画などの視覚情報は文字よりも多くの情報を伝えることができ、臨場感も生まれます。学習障がい(読字障がいなど)や身体障がい(視覚など)がある学生にとっても、音声読み上げ機能などがついたデジタル教材は学びの補完に大きく寄与します。
また、事情により講義に出られない学生や、一度の講義では理解できなかった学生に対しても、正規の時間外に学習できる環境を提供できることもメリットです。
教職員の業務効率向上につながる
大学の教職員は、出席確認や提出物管理をデジタル化することで、円滑な授業運営ができるようになります。テストもデジタル化してペーパーレスにすることで、採点を自動化できたり、印刷のコストを削減できたりします。
外部の教材やコンテンツを使用することで、講義そのものをアウトソーシングすることも可能です。My CareerStudyなどを利用して単位認定をおこなう大学も増えてきています。
また、学習活動を一括管理することで、学生の履修状況や成績などのデータを収集し、学生全体の総合的な分析をおこなうこともできます。その分析結果は、大学のブランディングの向上や、学生募集などのマーケティング戦略の立案にも活用できます。
デジタル学習を活用する際の注意点
デジタル学習は新しい手法であるため、留意しなければならないこともあります。ここからは、デジタル学習を活用していく際の注意点について解説します。
学生のデジタルリテラシーには差がある
学生のデジタルリテラシーには個人差があり、その差が学習の進捗や成績に影響を与えることがあります。
特に、大学独自の履修登録システムや学習管理システム(LMS)などは、初めて扱う学生にとっては操作が難しいと感じる可能性があります。そのため、こうしたツールの使い方についてのガイダンスを実施するとよいでしょう。
また、デジタル技術を使用している以上、ネットワーク上の不具合によって授業に参加できない、各種手続きができないといったトラブルが起こり得ます。そのためトラブルが起きた際の対処法についてもガイドラインなどで事前に周知しておくとよいでしょう。
さらに、学生に指導するだけでなく、指導する側である教職員に対するデジタルリテラシー教育もおこなうことが求められます。
人によって学びの定着度が異なる
デジタル学習は紙による学習と比べて理解しやすいと評価する人もいます。一方で、「文字を書く」「付箋を貼る」といった五感を刺激する工程がデジタル学習には少ないため、情報が流れてしまい、記憶に残りにくいと感じる人も少なくありません。
デジタル学習は新しい学びのスタイルのため、学習効果には個人差が生じやすいと認識し、学生の理解度を考慮しながらよりよい学習環境を検討するとよいでしょう。紙の教材を活用して理解を深めつつ、デジタルツールの利便性を生かした学習方法を取り入れるなど、効率的かつ効果的な学びにつなげていくことが大切です。
学習管理システムの改修が必要になる
多くの大学で利用されているLMSですが、講義の内容やカリキュラムの変更、講師の交代などが発生すると改修が必要となる場合があります。
またデジタル学習を活用する場合、学生や教職員が操作しやすいシステムデザインへの改善や課題の提出機能、担当教授がフィードバックを送るための機能の実装など既存システムの改修が求められます。
システム開発やデザインの専門知識を持つ人材の確保だけでなく、教職員への教育や学生へのサポートを通じてシステムの使いやすさを向上させ、スムーズな運用を実現することが重要です。
デジタル学習の活用事例
続いて、大学のデジタル学習の活用事例について紹介します。
段階的なキャリア教育カリキュラムの実施
2024年4月現在、11学部14学科5研究科を有し、約11,000名の学生が学ぶ関東学院大学では、同大学で推進する「社会連携教育」の枠組みのもと、より段階的に社会とつながっていく新たなキャリア教育のカリキュラムづくりに挑戦しています。
カリキュラムの構築にあたっては、マイナビが運営するMy CareerStudyを積極的に活用して学生が自身に足りないスキルや知識を都度修得できる環境を整えています。
1年次には、マイナビの「適性診断MATCH plus」を使って自身の強みや弱みを分析しながら、キャリア教育科目を受講してさまざまな業界についての基礎知識を学びます。その後、学内のPBL(アクティブラーニングを促す勉強法)を経験することで、考える力を身に付けていきます。
2年次では、学内だけでなく学外と融合したPBLを経験するステップを踏みます。着実に知識と経験を積み重ねることで、3年次では抵抗なく企業のインターンシップに参加するための基盤が整います。
詳しくはこちらをご覧ください。
「大学事例|身近なところから段階的に社会とつながる新しいカリキュラムへ|関東学院大学」を読む
オンデマンド型キャリア教育科目の新設
My CareerStudyを活用し、授業の合間などの隙間時間でキャリア教育を受けられるオンデマンド型の科目を新設した大学もあります。
この大学では、インターンシップへの参加や就職活動を見据え、年に複数回この科目を開講しています。
例えば、初回は社会人基礎力や、デジタルツールの基本的な使い方などを学びます。
他にも、自己分析や企業研究などの内容を学ぶ回もあります。
また、日々の大学生活でも活用できる「プレゼンテーション」や「グループディスカッション」に加えて、今後のキャリアについて学ぶ内容も盛り込まれています。
いずれも、My CareerStudyの動画学習と確認テストなどを活用しながら学習を進め、単位を修得するというカリキュラムです。
学生の課題に応じた個別指導の実施
デジタルを活用した「大学・高専教育高度化プラン」として、ある教員養成大学の取り組みを紹介します。この大学では、デジタル学習を活用することで、学生一人ひとりが自分のペースで学び、実際の教育現場で活かせる力をしっかりと身に付けられる仕組みを整えています。
具体的には、LMSや教育実習前CBT(コンピュータを活用した試験)を活用して学生の履修状況を可視化し、それぞれの課題に応じた適切な指導を実現しています。
また、教育現場で求められる知識やスキルを身に付けられるよう、実際の指導を想定したトレーニングをおこない、実践的な指導力を養う機会を提供しています。さらに、e-learning学習やオンライン授業の活用など、時間や場所を問わず学習できる環境を整備しています。
これにより、大学での授業と学校現場における教育実習などを効率的に結び付け、学びを深める工夫がされています。
デジタル学習をキャリア形成支援にどう活かす?
デジタル学習とLMSの活用により学生の履修状況を把握しやすくなっています。これにより、学生一人ひとりに寄り添ったキャリア形成支援が可能になるでしょう。
例えば、学生が講義を通じて得た気付きや講義後に調べた内容、理解度や課題の達成度などの学修成果を可視化することができれば、それらをもとに「何に興味を持っているのか」「どこでつまずいているのか」といった学生の状態を把握することができます。
こうした情報を参考にすることで、学生一人ひとりの特性や課題を明確にし、今後の目標を一緒に考える際の手助けにもなります。また、学生の興味や関心に合った業界や職種を紹介するなどの支援につなげられるかもしれません。
GIGAスクール構想などを背景に、今後大学に入学する学生は、すでにデジタル学習に慣れ親しんでいる人も多くなると考えられます。多様化の時代に生きる学生に対し、デジタルに基づいた適切な個別支援を提供するためにも、デジタル学習の重要性はますます高まっていくでしょう。
GIGAスクール構想については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
「GIGAスクール構想とは?目的やメリット、現状の課題」を読む
まとめ
デジタル学習は急速に日本の小・中・高校に浸透しています。そのため、デジタル技術を使って自主的に学ぶことや、学外のサービスを活用することに慣れた学生が増えていくことが予想されます。
キャリア・就職支援担当者は、デジタル学習のメリット、デメリットを正確に把握したうえで学生のキャリア形成支援につなげていきましょう。My CareerStudyなどのサービスを活用してオンデマンド型のキャリア教育講座を開催するのも選択肢の一つです。
ここで紹介した内容を参考に、キャリア形成支援におけるデジタル学習の活用をぜひご検討ください。
マイナビキャリアサポートでは大学のキャリア・就職支援担当者向けの情報を発信しています。ぜひご活用ください。
「マイナビキャリアサポート」は
キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです
長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。
より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。