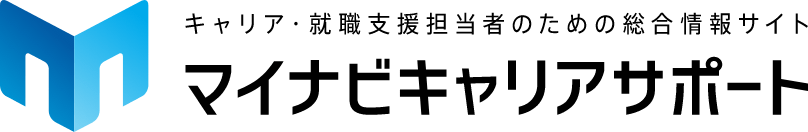叡啓大学は、未来をつくる人材を育てる大学として、2021年に広島県にて開学しました。授業とキャリア教育がシームレスになっているのが特長で、在学中の4年間を通じて社会や企業とのつながりを学び、キャリアに向き合う教育プログラムを軸としながら、多種多様なキャリアを支援するプログラムを実施しています。2024年度が初の卒業生輩出となった叡啓大学の社会で新たな価値を創り出すために必要なコンピテンシーを身に付けるキャリア支援の秘策について、キャリアデザインオフィス担当教員である松浦氏にお話を伺いました。
Profile
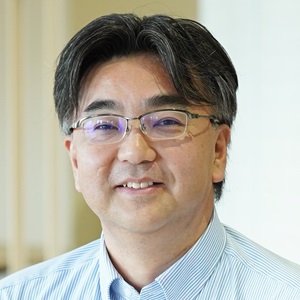
松浦 康之 氏
叡啓大学 キャリアデザインオフィス担当教員 / 課題解決演習(PBL)担当教員
大学院卒業後、電機メーカーでソフト開発に10年以上従事したのち、起業。その後、広島県の支援のもとバイオデザインを学びにインドへ渡航する。帰国後は広島大学を経て、叡啓大学へ。起業やスタートアップでの現場ニーズに基づくサービスやデバイス開発経験を活かし、課題解決演習(PBL)の担当教員と起業家の二足のわらじで実務家教員として学生たちの支援を行う。
叡啓大学の教育の重要な柱の一つであるキャリア教育・支援

―叡啓大学のキャリアに対する考え方から教えていただけますか?
叡啓大学では4年間を通じて社会や企業とつながり、学生が自身のキャリアと向き合う教育を実施しています。授業はもちろん、授業外の様々なキャリア支援プログラムにも力を入れています。
というのも、私たちの教育課程そのものが、将来にわたって自ら学び、自ら仕事を創り出し、社会にイノベーションを起こすことができる「未来をつくる人材」を育てるという理念のもとで行われているからです。
だからこそ、キャリア教育もキャリア支援も教育の重要な柱の一つ。卒業後の希望進路について考える力ではなく、大学時代や社会に出た後の行動や意思決定も含め、学生一人ひとりが自らのキャリアを自らデザインできる力を養えるように設計しています。
―自らのキャリアを自らデザインする力の養成が重要なのですね。
そうですね。その力を育むため、特に私たちはアントレプレナーシップ育成を土台に、新しいことに取り組む姿勢やスキルを学べる機会を数多く用意しています。
ちなみに、ここでいうアントレプレナーシップは起業家精神というより、どんな環境でも主体的にチャレンジし続ける精神といった広義な意味で使っています。社会に出た後のキャリアも多種多様かつ複雑になっており、健康寿命も伸びるなかで様々なことに挑戦できる時代だと思っています。
叡啓大学で学んだ学生には、自分でやりたいことを見つけ、そこに至るプロセスも考えることで、リスクを恐れず新しい一歩を踏み出し続ける人間になってほしいと考えています。
2年生からの課題解決演習とアクティブ・ラーニングの徹底

―具体的には、どのような取り組みを行っているのですか?
アントレプレナーシップ教育関連の授業でいえば、2年生から本格的に始まる課題解決演習には力を入れています。本学は叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会を構築し、地元の広島県だけではなく、全国で事業を展開する企業、自治体、NPO、国際機関を中心に、実際に直面しているリアルな課題を提出していただきます。その課題を学生3〜4人のチームで分析し、解決すべき重要な課題を特定し解決策を提案していく演習です。
授業の最後には、連携先様からのフィードバックの機会も設け、さらに改善案の提案まで行うのですが、この演習は学生側からも企業側からも高い評価をいただいています。
また、こうした実践形式の演習の効果を高めるため、叡啓大学では1年生の時からアクティブ・ラーニングを推奨しており、すべての科目でグループディスカッションやプレゼンテーションを実施しています。インプットしたことを常にアウトプットすることを意識させている点も特長かもしれません。
気軽に参加できるイベントから、挑戦をサポートするネットワークまで

―キャリア支援でも様々な特長的なプログラムを実施していると聞いたのですが、いかがですか?
最も学生の参加ハードルが低い取り組みからお話しすると、数ヶ月ごとに、「イブニングラウンジ」という場を設けています。これは社会の第一線で活躍されている方々をゲストとしてお招きし、自身の仕事の内容やキャリアに関してお話ししていただくというものです。
授業終了後の夕方以降の時間帯で、かつ自由に参加できるため、興味のあるテーマやゲストの時にふらっと参加する学生も少なくありません。また、他学年の学生や留学生、外部から聴講に来た社会人など、普段の授業や大学生活では接する機会の少ない人たちとの交流の場としても賑わっています。
―他には、どういった取り組みがあるのですか?
「キャリアメンター制度」も、叡啓大学ならではの取り組みではないでしょうか。NPOやNGOなどを立ち上げた社会起業家をはじめ、様々な業界や分野の第一線で働く企業人や個人事業主など、年代も幅広く20代から60代まで、学生が興味を持ちそうな社会人の相談ネットワークを整えています。
在学中から就職先や興味がある業界などのキャリアに関する相談に加え、自分たちが挑戦しているボランティア活動、イベントの実施、ビジネスといったプロジェクトについての相談などもすることができ、学生たちが新しい一歩を踏み出すための大きな役に立っていると自負しています。
もちろん、日頃から叡啓大学の教員や職員もチャレンジしようとしている学生を応援する風土がありますし、そうして学内に挑戦の風土ができあがることで、最初はなかなか新しい一歩を踏み出せなかった学生も刺激を受け、成長している場面を数多く見かけます。
社会で生き抜くコンピテンシーを身に付けた卒業生の進路は多種多様

―ちなみに、一期生となる2024年度卒業生の進路や見えてきた効果はいかがですか?
卒業生の進路は想像していた以上に多種多様ですね。就職先の業界も多岐にわたりますし、最初から起業する卒業生やフリーランスで個人事業主として社会に出ていく卒業生がいる点も頼もしい限りです。
こうした結果を見ると、学生たちの幅広い興味に対し、それぞれが進みたい道に進む力を養うことが、初年度からある程度できたのではないでしょうか。その一方で、これだけ多種多様なキャリアの志向が混在すると、学生一人ひとりに寄り添って支援していくことの難しさも感じています。
今後は、これまで以上に様々な企業や社会人とのネットワークを構築し、学生と社会の橋渡しのバリエーションと強度を高めていきたいですね。
―最後に、他大学の皆さまへメッセージをお願いします。
新しく開学した大学のため、キャリア支援への取り組みはまだ始まったばかりです。
学生のチャレンジ精神をしっかりサポートしていけるよう、他大学の皆さまからキャリア支援やネットワークの構築などについても、もっと学ばせていただきたいと思っております。
皆さまのお力を借りながら、叡啓大学のキャリアデザイン教育を育てていけるよう努めてまいります。
Editor’s Comment

叡啓大学 キャリアデザインオフィス担当教員の松浦先生を取材させていただきました。取材後に感じたキャリア支援のイメージは「インタラクティブ」というキーワードでした。学生に対して一方通行的な講座提供や支援だけではなく、中心となる学生を取り巻くように、教員、職員、企業、自治体、地域社会が学生に近い位置に存在し、日々PBLなどで双方向に関わっているイメージが浮かびました。また、普段から学生自身のアウトプットの機会を多く設けることが、 より主体的な学生生活を送ることにも通ずるのだと感じました。 しかも、それが学業からキャリア形成にシームレスに繋がっているとも感じました。
(マイナビ編集長:高橋)
「マイナビキャリアサポート」は
キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです
長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。
より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。