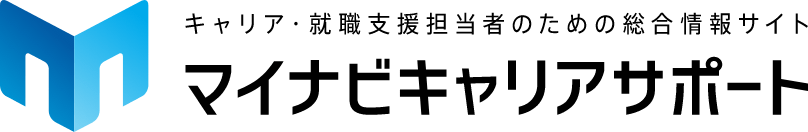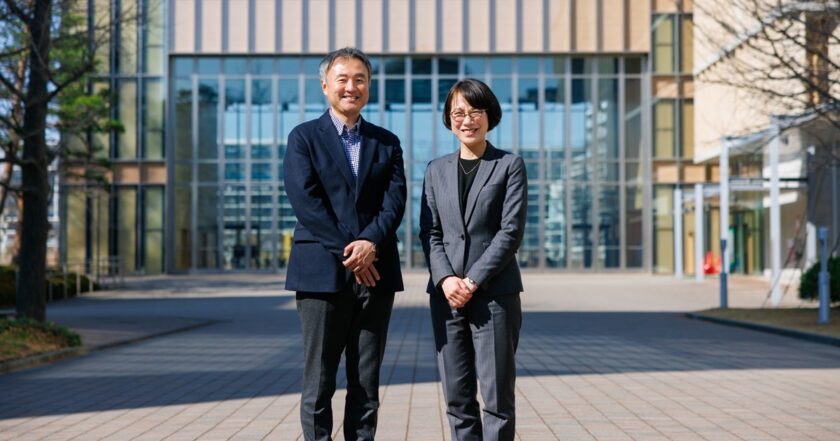1883年に創立された獨逸学協会学校を起源に持ち、獨協学園創立80周年を機に設立された歴史ある獨協大学。外国語学部・国際教養学部・経済学部・法学部の4学部11学科、大学院3研究科を置き、全学生数は約8,600名。創設者天野貞祐の「大学は学問を通じての人間形成の場である」を建学の理念とし、社会の要求する学術の理論および応用を研究、教授することによって人間を形成し、あわせて獨協学園の伝統である外国語教育を重視して今後の複雑な国内および国際情勢に対処できる実践的な独立の人格を育成することを目的としています。キャリアセンターでは、学生の自律と五感を大切にサポートしており、多様な学生に合わせた年間350コマの講座やイベントを開講しています。今回は、そんな獨協大学のキャリア支援について、キャリアセンター所長の鈴木氏と課長の大田氏にお話を伺いました。
Profile

鈴木 涼太郎 氏
獨協大学 キャリアセンター所長 / 外国語学部交流文化学科 教授
大学卒業後、旅行会社に勤務し、法人営業職を経験。在職中に大学院に進学したのち、博士課程後期課程修了。相模女子大学学芸学部を経て、2014年より獨協大学で勤務。専門は観光研究、観光文化論、観光人類学。2024年4月よりキャリアセンターの所長を務め、キャリア支援に携わる。

大田 裕子 氏
獨協大学 キャリアセンター課長
補助金業務や大学広報、教務を経て、2016年よりキャリアセンターにてキャリア支援に携わる。2022年から現職。学生相談やガイダンス・講座等の企画・運営を担い、企業・団体との関係構築にあたり、常に学生にとって何が必要かを考えながらキャリアサポートを行っている。
対面だからこそ生まれる、リアルな感覚や熱量も

―キャリア支援を行うにあたって心がけていることはありますか?
鈴木:学生が主体性を持ち、五感を使って活動することを最も大切にしています。今や、ウェブであらゆる情報が手に入り、コロナ禍以降はオンラインでの就活イベントなども増えました。しかし、そんな今だからこそ、人と人との直接のコミュニケーションで生まれるリアルな感覚や場の雰囲気、熱量を肌で感じてほしいと考えています。学生も自身の目で見て、耳で聞いて、肌で感じることで、自分のキャリアについてより深く考えることができるのではないでしょうか。そこで、獨協大学ではできる限り対面でのキャリア支援を心がけています。
大田:対面の個別相談を予約なしで受けられるようにしているのも、そのためです。学生が相談したいときに、いつでも気軽に立ち寄ることができるキャリアセンターでありたいと考えています。キャリアセンターの場所も、学生がキャンパス内でよく訪れる図書館や学食の導線上に配置され、獨協大学では学生と教職員が近い距離でコミュニケーションがとれるように工夫しています。
学生の反応を見ながら、タイムリーかつスピーディに形にできる
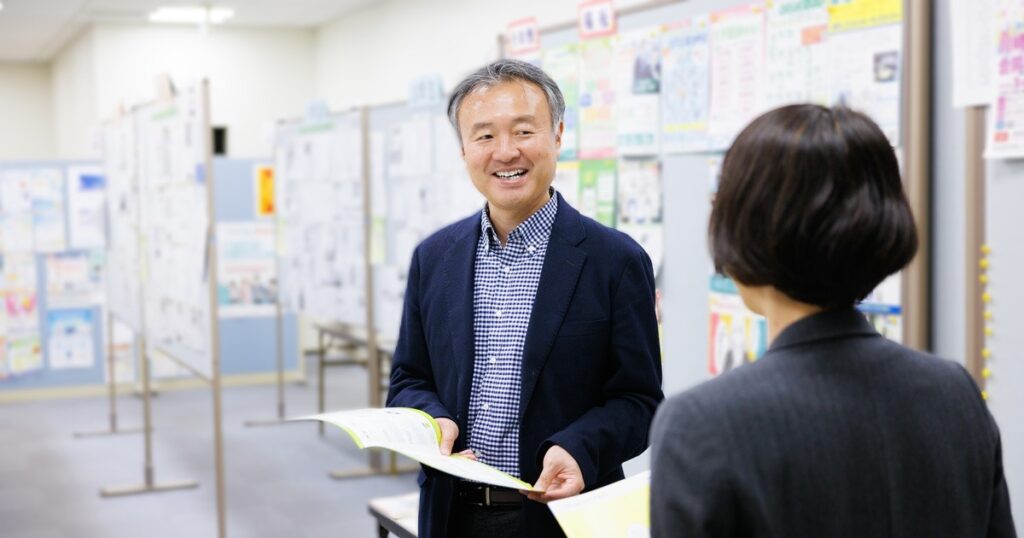
―個別相談以外は具体的にどのようなサポートを行っているのですか?
鈴木:年間80講座、約350コマの講座やイベントを開講しています。学生の自己理解を促進するべく必要な支援を、必要なタイミングで実施することを意識しながら、講座の内容や実施時期も毎年見直しています。こうした柔軟な対応ができるのも、普段から対面で学生たちのリアルな反応を見聞きできているからです。最近特に人気なのが、全学年を対象とした「職種から考える就職活動」という講座です。キャリアを考える最初の入口を、業界ではなく職種にフォーカスを当てることで、学生たちの視野を広げることを意図しています。ジョブ型採用など、これまで以上に「どんなプロ(職種)として成長していくか?」ということも問われる時代ですからね。
大田:ちなみに、この講座は獨協大学の卒業生で民間企業に就職した経験のある職員が企画しました。「『自分がどんな働き方をしたいのか』を軸に、『どの職種が自分に合いそうか』を考えることで業界への理解を深めて欲しい」と感じて企画してくれたのです。また、対面で学生の反応を的確に把握することに加え、若手職員をはじめ、誰もが意見やアイデアを出し、タイムリーかつスピーディに形にできる体制を整えていることも大きな特徴だと考えています。
在学中に対面で築いた関係性が、卒業生の大きなサポートを生む

―他にはどういった取り組みを行っているのですか?
大田:キャリアセンター主催のイベントでは卒業生に登壇してもらうなど、卒業生と学生が交流できる機会も数多く設けています。先ほど触れたように、気軽に利用できる対面のキャリア支援を長年実施しているからこそ、卒業生とも在学時代から良好な関係が構築できており、卒業後も声を掛けやすいのです。業界や職種、年齢も幅広いですし、やはり、卒業生のリアルな声は学生にもよく響きますね。
鈴木:卒業生と交流できるイベントは低学年から参加できるため、学生が視野を広げるきっかけにもなっていると感じます。卒業生と交流することで、興味のある企業だけではなく、BtoB企業などを知るきっかけとなり関心も高まりますし、今後はこういった企画もより積極的に開催していきたいと考えています。
学生生活も含めたサポートや、差別化を意識した講座・イベント開発を

―では、学生を支援する中での難しさや課題だと感じる部分はありますか。
鈴木:獨協大学は4学部11学科あり、それぞれの学生にカスタマイズしたサポートを行っていくことが今後の課題だと感じています。学部によって学生が興味のある業界の傾向も異なりますし、就職活動の進め方も変わってきます。たとえば、外国語学部では海外留学を視野に入れている学生が多く、留学のタイミングなどの見極めも重要になってきます。
大田:私たちも「貴重な4年間、充実したキャンパスライフを送ってほしい」という強い想いが根底にありますからね。学業や留学、課外活動なども含めて学生生活を充実させることが将来への視野を広げ、キャリアを考えることにも直結してくると考えています。
鈴木:また、様々なニーズに対応する講座やイベントを実施していますが、学生の参加が芳しくなく、苦労しているものもあります。そういった講座やイベントは、おそらく他のものと差別化が上手く図れていないのだと感じています。どういった学生のための、どんな内容の講座やイベントなのか。内容の差別化はもちろん、開催時期や場所、告知方法も常に試行錯誤しながら改善しています。
―最後に、他大学の皆さまへメッセージをお願いします。
大田:キャリアセンターの役割は、学生自身が自分のキャリアを築いていく過程を常に伴走することだと考えています。学生の価値観も多様化している中、一人ひとりの考えをしっかりと理解し、学生生活を含め、キャリア形成のサポートを行っていくことは簡単ではありませんが、ぜひお互いに尽力していければと思っています。
鈴木:一つの大学だけではできることにも限界があると感じています。皆さまは、学生と社会をつなぐ同じ立場の心強い仲間です。大学同士の横のつながりも大切にしながら、皆さまと一緒に成長していけたらと考えています。
Editor’s Comment

獨協大学キャリアセンターの鈴木所長、大田課長を取材させていただきました。印象に残ったキーワードは「五感」でした。全国の各大学でも、学生へのアプローチや支援についてさまざまな取り組みをされていますが、獨協大学では、キャリアセンターが学生の往来が多い場所に位置し、ドアはいつもオープンで、常に音楽が流れ、ふらっと立ち寄り易い雰囲気作りを心掛けているそうです。悩みが深刻になる前に、気軽に相談して欲しい、というメッセージが伝わってきました。多様な学生に対する支援への方法はひとつではありませんが、人間味のある温かい支援は、どのような学生に対しても、共通して行うことのできる支援方法だと気付かされました。
(マイナビ編集長:高橋)
「マイナビキャリアサポート」は
キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです
長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。
より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。