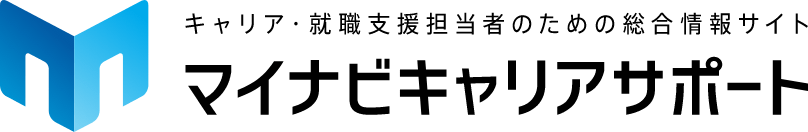1935年に創立した千葉県柏市の麗澤大学は、国際性を重要視した教育を行っており、世界18カ国からの留学生と共にキャンパスライフを過ごせることも魅力のひとつです。2024年には、新たに経営学部と工学部の 2学部を新設し、現在は外国語学部、経済学部、国際学部と併せて5学部体制に。また、教員と学生の距離の近さが叶う少人数制の教育にこだわる麗澤大学では、キャリアサポートも一人ひとりに合った支援を実現しています。今回は、そんなグローバルな社会を生き抜く力を養う、オーダーメイドな支援とユニークなキャリアサポートについて、大学事務局の石光氏にお話を伺いました。
Profile

石光 俊明 氏
麗澤大学 事務局 副部長
2003年に入職して経理を担当したのち、2007年よりキャリアセンターで勤務。以降、就職支援業務と共にキャリア教育科目の企画・運営も行い、2017年より非常勤講師として科目の運営を統括している。2023年からは大学事務局副部長として、キャリア支援だけでなく、学生相談室及び障がい学生支援課も管轄するなど、多様な学生のサポートに関わっている。
全員面談の最大の目的は常に学生の味方でいること

―まずは、注力しているキャリア支援について教えてください。
最も注力しているのは、個人に合ったオーダーメイドなキャリアサポートを行うことです。学生ごとに将来の希望や置かれている状況は異なるため、一人ひとりに合ったキャリアを構築していく必要があると考えています。
さらに、麗澤大学は一学年で660人程です(2024年度からは学部増加に伴い1年生は一学年800人程)。少人数制の強みを生かし、全員面談を実施していることも、大きな特徴です。
全員面談の対象は3年生で、4月から学生たちと連絡を取り、希望している就職先を確認したり、今後の就活スケジュールを伝えたり、また心構えなどをアドバイスする機会にもなっています。
もちろん、連絡が取れなかったり、面談に参加しなかったりする学生も少なからずいますが、教員との連携や粘り強いサポートを行い、3年生の12月頃には全学生のうち95%の学生と面談を実施しています。
―かなりの割合ですね。面談でとくに意識していることはありますか?
学生は、すでに自分の中にある選択肢の中から将来の希望を考えがちなため、できるだけ学生の視野を広げることを意識しています。
たとえば、語学を学ぶ学生にとっては観光系の仕事を思い浮かべやすいですが、商社や物流業など国際性も高く、卒業生が活躍している企業などの紹介です。さらに、福利厚生や給与の話も交え、学生がより様々な業種に関心を持ちやすいような工夫もしています。
しかし、実際に行動し、決定するのは学生本人であって、私たち教職員ではありません。私たちは常に傾聴の姿勢を忘れず、学生の意思を尊重し、サポートを全力で行うこと、とにかくそれだけですね。
最後には学生自身が自分で考えて決めるタイミングが来ますので、常に学生の味方でいるということを心がけていますが、自分だけでは動き出せない学生も多いのが現状です。そこで、就活ゲームという手法で、学生たちの行動力の促進にも努めています。
学生の主体性を磨くきっかけづくりの秘策とは

―就活ゲームというワードが気になったのですが、詳しく教えていただけますか。
麗澤大学には「キャリア形成入門」という科目が3年生前期にあるのですが、これはキャリア教育と就職活動を連携させたような科目です。このなかで、授業で学んだ就職活動の進め方や企業の選び方を学生が実践できるように促す取り組みとして就活ゲームというものを取り入れています。
具体的には、就職活動に関する様々な行動をポイント化し、そのポイントを集めることで評価の一部とするようにしています。たとえば、エントリーシートを書いてキャリアセンターで添削したら3ポイント、実際にインターンシップや企業セミナーに参加したら企業ごとに5ポイントというような形です。
5ポイントを1点に換算して点数化することで、最大の500ポイント累積した場合は100点に換算され、高評価につながります。
また、麗澤大学の卒業生が活躍している企業を中心とした学内合同企業セミナーを開催しているのですが、このセミナーに参加することで得られるポイントのウェイトを高く設定することで、3年生の6月という早い段階でのセミナーの参加率を上げています。
キャリアを構築するときに必要なものは、行動力ではないかと思っています。自分の人生を自分で考える。そして、とにかく動いてみる。この就活ゲームは、早い段階で学生がその一歩を踏み出す後押しになっていると感じています。
―就活ゲームを取り入れたことで見えてきた効果や学生からの評判はいかがですか?
効果としては、インターンシップやキャリアセンター主催のイベント参加率が格段に伸びたことが挙げられます。就活ゲームを取り入れる前には、3年生の夏休みにインターンシップやキャリアセンター主催のイベントに参加する学生は50人程でした。
しかし、現在では、200人以上が参加しています。ポイントを稼ぐために参加しているという学生もいると思いますが、キャリアや就職を考える契機になったというメリットも考えられます。
また、履修後のアンケートでも、早期からキャリアについて考えて行動することができたといった肯定的な意見が多く、学生に対する良い効果を感じています。
在学中だけでなく生涯寄り添い続けるキャリアサポート

―キャリア支援を行っていくうえでの課題はありますか。
全員面談や就活ゲームなど、学生が早期から将来のキャリアを考える仕掛けを用意していますが、それでも就活に前向きになれない学生は一定数います。
昔は、そういった学生をどうやって動かそうかと考えていましたが、それは逆効果だと気づきました。今は、学生自身が自分から動き出すのを待つようになりましたね。
ただ、いざ動こうとした時にいつでも気軽に相談できる環境や関係は構築するようにしています。一方で、早く動いて早く就職先を決めすぎることも課題に感じています。
というのも、麗澤大学の学生に勧めたい企業があっても、学生がこうした企業と出会わないまま就職活動を終えてしまうことがあるのです。この点は企業とも連携し、今後少しでも改善していきたいです。
―なるほど。ちなみに、低学年に向けたキャリア教育や支援はどのようなことに取り組まれているのですか?
1年生や2年生を対象にオムニバス形式の授業を行っています。内容としては、コミュニケーションのとり方やスケジュール管理の方法などの基礎的なことから、マネーリテラシーやITリテラシーなどの将来役に立つスキルです。
またスキル面だけでなく、麗澤大学の理念である道徳を通じた社会との関わり方や、大学の有効活用方法といったことも伝えています。
就職支援というより、キャリア構築の観点から様々な知識を増やすことで、自分自身でその後の人生のより良い選択ができるようになってほしいという思いがあります。
学生の未来のために変革期を乗り越える勇気ある一歩を

―今後、挑戦したいことはありますか。
実は、ちょうど今、卒業する学生に向けた最後のキャリア教育を計画しています。2028年に開講予定なのですが、卒業後でも気軽に帰ってこられる場所として大学を位置付けられるような授業を展開したいと考えています。
現在行っている支援だけではなく、転職の相談などでも力になれることはありますし、困ったことがあった時に頼れる存在でいたいですよね。卒業生のサポートまで力を入れることは、在学中の学生たちにもメリットがあると思いますし、良いサイクルが生まれるのではないかと考えています。
麗澤大学に入学したことを在学生や卒業生全員に誇りに思ってほしい。キャリア支援は在学中に限ったことではないので、そういった意味での学生の生涯のパートナーになれるような授業ができればと試行錯誤しているところです。
―最後に、他大学の皆さまへメッセージをお願いします。
まずは、日頃から学生の未来のために奮闘されている皆さまに同業者として心から敬意を表したいです。近年、就職活動の様相は変化しており、日々悩みながらキャリア支援・就職支援に取り組んでいる方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、大学によってはキャリア教育の運営も行い、職員でありながら教育を行うという方々もいらっしゃるかと思います。大学の就職支援部署は、今まさに変革期にあると思います。そんな時代を乗り越える一手を麗澤大学でも試行錯誤しています。
それぞれの大学で正解は異なると思いますが、未来を担う学生一人ひとりのより良いキャリア支援を実現したいという想いは皆さま同じだと考えています。
今後も切磋琢磨しながら、一緒にこの変革期を乗り越えていきましょう。そして、同業の皆さまのキャリアもまたより良いものでありますよう、心より願っております。
Editor’s Comment

大学事務局の石光副部長に取材させていただきました。「学生が100人いれば100通りの支援が必要である」というお言葉に、当初私は「でもそれを実践することは難しいのでは?」と感じました。
しかし、学生相談室や障がい学生支援課も管轄され、キャリア科目の非常勤講師をされて、多様な学生と直に接しているお立場からのお言葉なのだと腑に落ちました。
そして、「人を変えるのは難しい」ということを前提に、「変えることは難しいが、きっかけを与えることはできる」と、粘り強く、学生と同じ視線で各支援に取り組まれているお話を伺い、家族のような温かみを感じました。
就活ゲームという取り組みも、実は多様な学生に対する最大公約数的なプログラムなのだと思いました。
(マイナビ編集長:高橋)
「マイナビキャリアサポート」は
キャリア支援・就職支援に関する総合情報サイトです
長い学生生活の出口で、学生たちを社会へと送り出す。その大きな役割と責務を担っている皆さまに寄り添い、活用いただける情報をお届けするため、2022年にサイトをリニューアルいたしました。
より良いキャリア支援・就職支援とは何か。答えのないその問いに対して、皆さまの学生支援のヒントとなるような情報をお届けして参ります。